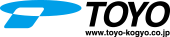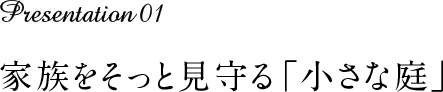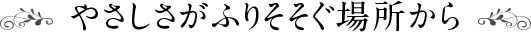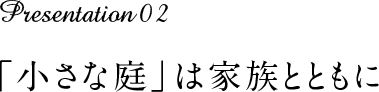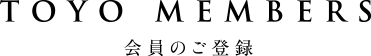庭は、忙しい毎日のなかでホッと一息つける場所。そして、家族が積み重ねていく、いくつもの時間に寄り添う場所。春夏秋冬、季節がめぐるたび一つひとつ思い出が刻まれていく庭は、いつしか家族にとってかけがえのない特別な場所になっていく。
手をかけ、育み、慈しむ。それは、どこか子育てにも似ている。そのときによって、庭の役割も、庭との距離も変わってくるという点でも。子どもが小さいときはあまり手のかからない草木を中心にして、遊ぶためのスペースも確保しておきたい。大きくなってきたら、そのスペースは家族団らんのためのテーブルを置き、季節にあった一年草を増やしていくのもいい。そのとき一番心地いいように変化していける、それが小さな庭の大きな特徴だ。
これからお届けするのは、「小さな庭」にまつわるある家族の物語。
夢や理想が一人ひとり違うように、庭のある暮らしがもたらすものも家族それぞれで違います。
小さな庭と、そこで感じる幸せな時間。家族の風景を覗いてみましょう。

娘が生まれたのは、クリスマス間近の午後だった。
「ワーク・ライフ・バランス?ないない」と言っていた僕がそそくさと家に帰るようになったのは、まぎれもなく娘のせい。
「光輝のときは出張ばっかりだったのに!」と妻はしばらくブツブツ言っていたが、働きながら幼いふたりの子育ては想像より大変だと気づいたのだろう。
それからすぐにお弁当作りと保育園の送り迎えが、僕の日課となった。
いくつかの春がめぐり、息子が小学校にあがると、朝夕の保育園までの道が僕と柚奈のデートコースになった。
春には、つくしやたんぽぽを探しながら歩き夏の暑い帰り道は、たまに寄り道してカフェで並んでパフェを食べる。
秋にいろんな形の紅葉を拾って宝物箱に入れるのも、僕には新鮮だった。
遅れた冬の夕暮れ、保育園に迎えにいくと心細そうな娘が門のほうを見つめていた。
走っていくと、まるで花が咲いたような顔をして、駆け寄って飛びついてくる。
「今日、お友だちがみんな早く帰っちゃったの…」「そんな気がした」
「パパはゆずのこと、ぜーんぶわかるんだね。正義の味方みたい」
その瞬間、僕は、この笑顔を守りたい、と思ったんだ。とあとで妻に話すと、妻は「ゆずだけ?」とちょっとスネたようなフリをした。
その翌朝のことだ。
「お庭があるおうちがいいよねー」「そうね、憧れるけどね」
「きっと叶えてくれるよ、だってパパはヒーローだもん!」
瓜二つのまんまるな目をした最愛の妻と7歳の娘が僕を見つめてくる。
新聞に折り込まれていた近くの住宅地のチラシが、この話題のきっかけだ。
「まあ、見るだけ行ってみる?」ふたりに喜んでもらおうと、つい言ってしまった僕を呆れたように見上げる、僕によく似た息子11歳。
こんな調子だもんだから、モデルハウスでは女性陣の思うとおりに話が進み…。
僕は、家を建てることになった。
「やっぱり庭はいるね」「やった!僕、犬が飼いたかったんだよ!」
そうして、できるかぎりみんなの希望を全部入れた庭ができあがった。
引っ越しをしたころから妻は仕事に、息子はサッカーにと忙しくなった。
僕と娘は、庭で一番光があたる場所に柚の木を植えた小さな庭で過ごすことが増えた。
春には、冬を越したハーブの手入れをし、夏の暑い日は、ビニールプールを出して水浴び後にはアイスを食べる。
秋に押し花を並べたアートをつくるのも楽しかった。
年に幾度かしか降らない雪が庭に積もった朝は、早起きして雪うさぎをつくった。
いくつもの年が過ぎて、娘が中学生になると一緒に遊ぶことはなくなったけれど本を読んだり、犬をなでたりと、休日になると庭で思い思いに過ごした。
それがなんだか心地よかった。友だちと仲たがいしたと聞いた日には黙ってハーブティをそっと置いた。すると、僕を見上げて娘が言った。
「パパはやっぱり、ゆずのヒーローだね」

「10年って、あっという間だな」と傍らの犬に話しかける。
家を建てた時にはまだ小学生だった息子は就職活動中。
妻は相変わらずバリバリ働いていて去年、会社で初の女性部長になった。
僕は5年前に独立し、自宅の近くにデザイン事務所を構えている。
スラリと長身の娘は、我が娘ながらかなり目を引くタイプだが妻曰く「ああ見えてかなり真面目で堅物のモテにくい女」らしい。
「パパ、話があるの」「お、珍しいじゃん。どうしたの?」
手早くハーブティを入れて話を聞くことにした。「なんかあった?」。
「進路のことでママと喧嘩した」。
娘が相変わらず花や植物に興味があるのは知っていた。
「だからって北海道は遠すぎると思わない?」と妻から昨夜、聞いたところだ。
「パパに加勢してほしいんだろ?」「うん」
ほら、花が咲いたように笑うのだから、敵うわけがない。
目を輝かせて未来を語る娘に、反対できるわけがないじゃないか。
「わかった。ママのことは説得するよ」。
寂しいなんて言えるわけがないじゃないか。


進学先の合格通知が届いて、春から北海道に住むことが決まったのは、もう冬も終わるころだった。
「合格したよ」と告げると、パパは笑って「うん、よかった」とだけ言った。
「パパって気のきいたこと何にも言わないよね」ママにそういうと「そうねぇ」と笑う。
「仕事でいろいろあっても余計なアドバイスはしないし、いつもと変わらないの。でも、家のことができてなくても責めたりもしないの。あなたも、ずっと働くなら過剰に与える愛情より、そっと見守る愛情を持っている人を選ぶことね」。
中学生のころ、学校が嫌になった時期があった。
今考えれば、たいしたことではなかったような気がするけれど、ある日、どうしても行きたくなくて、家に戻ったら、会社に行くところだったパパと出くわしてしまった。
パパはおもむろにスマホを取り出していくつかの電話をかけ
「パパさ。今日は家で仕事することにしたよ」とだけ言った。
それからしばらくの間、パパは家で仕事をし、私は庭で犬と遊ぶ毎日を過ごした。
高校生になって、好きな人ができた。
部活の先輩で、誰にでもとても優しくて、いつも輪の中心にいる、1つ上のイケメン。
でも、卒業まで何にも言えなくて…そしてある日、大学生になった彼に彼女ができたことを知った。
落ち込んでいる私にむかって「みんなに優しい男は、モテるもんなぁ」といい
「もう!慰めてほしいのに!」と私が怒ると、へへへ、と笑ったパパ。
でもそれが本当の優しさではない、と気づいたのは、それからも彼がみんなに「彼女?いないよ」と言っていたからだった。


庭のテーブルで紅茶を飲みながら、思い返してみて気づく。
保育園のときも、小学時代も、中学時代も、そして高校生になっても。
悲しくてつらくなったときには、パパがいつもそばにいた。
何にも言わないからわからないけれど、黙って助けてくれていたんだ。
いつもちょっとふざけているけど、それは相手に負担をかけないようにだ。
それって…実は、すごいことなんじゃない?そうママに言うと
「でしょう?だってパパはママのヒーローだもの」とドヤ顔が返ってきた。
引っ越しの日は快晴だった。庭で犬と遊んでいるパパにコーヒーを持っていく。
「なんだよ。せっかく晴れてんのに、雨が降るぞ」お別れだというのに、いたって普通だ。
「そんなに離れているわけじゃないよ」はいはい、パパならそういうと思った。
「ここにみんなとの思い出があるから、いいんだよ」今度は少し照れたように言う。
「ゆずは、人のことをつい気にしちゃうだろ。自分の好きなものやひとに出会って自分が好きって思うことをすればいいんだ。パパはずっとここにいるから」。
呆れた。実は、いつも人のことを考えて、寄り添ってくれていたのはパパのほうなのに。
ありがとう。と、言おうとしたら、言葉の代わりに涙がどんどんあふれてきた。
いつもここにいてくれる。その安心感が私をきっと強くしてくれる。
どこにいても、記憶のなかにあって、そして実際に足を運び、振り返れる場所がある。その事実は、めまぐるしく変わる毎日のなかで、変わらない力になる。どんなものも永遠に同じものはないけれど、培ってきた時間とともに醸造されていった記憶はずっとそばにあるもの。そして変わらずにそこにあるという安心感が人を強くするだろう。家族全員にとってのかけがえのない場所をつくることもまた、そこにいる人にとっての愉しみになる。いつでもおかえりなさい、といえるように、手入れをする。一年一年、大きくなっていくシンボルツリーとして実をつける果樹を植えるのもいい。実をつける過程を楽しみ、そして収穫して楽しむ。その作業もまた、離れている家族とつながっている気がするから不思議だ。