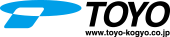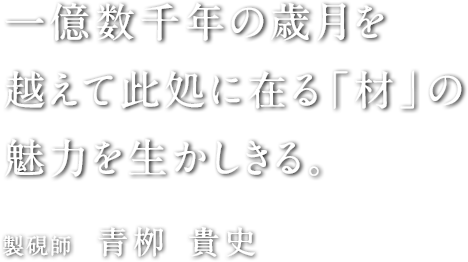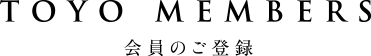「そもそも伝達のための道具として考案された最古のコミュニケーションツールなんですよ」。東京・浅草にある書道用具店「宝研堂」の四代目として生まれ、祖父・青栁保男氏と父・彰男氏に師事し作硯の深淵へと足を踏み入れた製硯師・青栁貴史さんは、その世界を極めようと模索を続ける製硯師。その仕事は、日本や中国の山に入り硯に適した石を探すところから始まります。山々の表情を見抜き、岩肌の声に耳を澄まし、地球の中に手を入れた石を、依頼者の要望に寄り添いながら何代にも渡って受け継がれるような硯へと進化させる。製硯という生業とそれにかける姿勢には、作庭との無数の共通項がありました───。
生涯をかけ、向き合い続ける。
祖父の背中から学んだ基本
祖父は工房の上に住んでいたので、小さいときから祖父の家に遊びに来るたびに、仕事場で硯をつくる祖父の姿を見て育ちました。仕事場に出入りするうちに、漆を溶く、研磨用具を作るといった、硯をつくる準備を手伝うようになり、そのうち、硯を磨いてみるかい?という祖父の提案から制作の一部に携わるように。高校を卒業するころには、硯を研ぐという作業まで手伝っていました。とはいってもノミに触ることはなく、技術的なことを教わった記憶はありません。今になって振り返ると、祖父は僕に技術を教えようとは考えてなかったように思うんです。僕が祖父から教えてもらったのは、硯と向き合う姿勢。その一言に尽きます。
祖父が生きた時代には関東大震災が起こり、太平洋戦争では浅草周辺も大空襲によって被害を受けました。戦争で友だちが何人も死んでいったという話を、祖父はよく僕に泣きながらしてくれたものです。祖父は最晩年、大動脈瘤の破裂で入院したのですが、痛み止めのモルヒネで意識がもうろうとなりつつも、僕に硯の彫り方を教えようとするんですよ。僕が看病をしていると、うわごとのように「そのノミを取ってくれ」「麻子坑の彫り方はこうだ」と話し出すんです。過酷な時代を乗り越えて生きたひとりの男性が、病室で亡くなる寸前に見ている景色が、この工房だということが僕にとっては衝撃でした。
それまでは漠然と、30歳まで全く違う業種で働いてから、硯職人の道に進もうと思っていたんです。ですがその病室で、ひとりの男がこのように生きてこのように亡くなったっていう生き様を見せてもらったことで、考えが変わりました。硯という仕事一筋に打ち込み生涯を終えていくひとりの男がいる。それほどの世界であると実感しました。それであれば一刻も早く取り組みたいと思い、すぐに大学を辞めこの世界に。以来、祖父の仕事への向き合い方、考え方が僕の礎となっています。
祖父が亡くなってからは父に師事し技術的なものを教わりました。父は一つひとつの仕事に細かく目が行き届く人なので、例えばノミはこういうふうに使うんだ、とか、こういうふうに使うと刀はダメになる、こう彫ると石がダメになる、という細かい部分まで技術を学びました。それから、これは祖父の代から変わりませんが、とにかく工房は綺麗に使う。一日の終わりに汚れたままで終わらない。そんな作業環境に対する考え方も受け継いでいますね。
山の表情を見極める目を持ち
墨を磨るにふさわしい石を見抜く
この石が硯になるか、ならないかということは、一概にはいえないんです。見抜けるようになるには経験を積むしかない。硯が採れるといわれている山に何度もお邪魔していると、共通した表情があることがわかってきます。硯の石が採れる山は、硯が採れる山の顔つきをしているんです。だから良材が採れる山の表情を知り、その山と顔見知りになっていくためにさらに足を運ぶ、その経験なくしては見る目は養えません。具体的にいうと硯の石が採れる産地の近くには必ず綺麗な渓流があるんですね。その渓流に潜ってみると、何十年前、百年前、千年前、とさまざまな年代の石が転がっています。その石を拾い上げて、サンプリングしていく。それを繰り返していくことで上流のどの地点からはがれ落ちてきた石かも少しずつわかるようになってくるんです。
先日の個展では、北海道の石で作った硯を展示しましたが、北海道で硯になる石を見つけたのは日本で初の出来事でした。3年半かかりました。山の表情を見てエリアを絞ったあと、北海道の地質学に詳しい方から伺った石質と僕の直感で見つけた山との合致ポイントを探して、そこからいざ山へ。そうやって鉱脈を探し続けました。硯の性能を付帯している石が採れる鉱脈というのは幅が数メートルという場合も多く、少し外れるともう硯にならないんです。さらにその中の上質な部分になると地球の中に自分の手を入れてみないとわからない。だからここぞというところの地表に露出している一部から中を推察し、探し当てていく。地道な作業ですが、それが素晴らしい石と出会うことのできる唯一の方法ですから。
 【左】端渓坑仔岩有眼天然硯板(たんけいこうしがんゆうがんてんねんけいばん)、【中】端渓麻子坑秋葉硯(たんけいましこうしゅうようけん)、【右】歙州眉子紋長方淌池硯(きゅうじゅうびしもんちょうほうしょうちけん)
【左】端渓坑仔岩有眼天然硯板(たんけいこうしがんゆうがんてんねんけいばん)、【中】端渓麻子坑秋葉硯(たんけいましこうしゅうようけん)、【右】歙州眉子紋長方淌池硯(きゅうじゅうびしもんちょうほうしょうちけん)
想いを伝えるための筆記用具。
難解さではなく本質を伝えたい
本来、硯も筆も、何かを伝達するために筆記するための道具が必要だからという理由から考案されたものなんです。僕は毛筆文化を有する漢字文化圏の最古の筆記用具を作っている継承者であり、みなさんはその筆記用具の使い手の継承者です。僕は、文化は守るものではなく、その時代その時代の人たちで鍛えて育てていくものだと思っています。ですので、筆離れの進む現代であっても、手紙を書くため、誰かに想いを伝えるための筆記用具だという本来の目的を今一度根付かせてあげる必要があると思って、メディアや講演会のご依頼にも対応するようにしています。
正直にいえば、守らなくちゃいけないものは道具や文化ではなく、もっと根本的なものだと思っています。それは「心の在り方」です。本質とどのように向き合うかという心こそ大人が守るべきもの。僕は硯と毛筆の世界を愛しています。だから硯というものの本質、特徴、便利なところ、不便なところなどを何の脚色もせずお伝えしたい。そもそも筆を持つのに大切なことは字の上手い下手ではない。緊張するものでもない。思い、事柄を伝え残すというシンプルなことだけです。難解で縁遠い世界だという誤解を解いて差し上げたい。硯と毛筆文化の本質の所在を明らかにしておくことも、現代に生まれた製硯師の仕事だと考えています。
材との流暢な会話術を持つ者が
時代を超えた名工となる
いい硯にはひとつの共通点があるんです。それは「材は変えられない」ということを知っている作り手の作であることです。「作」はいくらでも変えられますが、材料だけは変えられないんです。その性質も、特徴もいじることはできない。なので、材をどれだけ見ているか、材と会話ができているかが重要になります。素材と流暢に会話できるほど向き合った結果として、名硯というものが生まれる。過去に作られた名硯から、技術の先にある石との向き合い方を教わったのかもしれないですね。
一億六千万年もの歳月をかけて地球がつくった石を、僕がたった数か月間作業することで、その素材を台無しにするのか、それとも二千年、三千年、その先の人に愛されるものに転じることができるのか。自分が死んだあとも残るものに対しての責任を負うことが僕たちには課せられていると思っています。これからも一つひとつその方に寄り添った硯を作り続ける、それだけですね。その方が望まれるものが手持ちの石ではできない場合には、中国まで採りに行きたいから半年、一年待ってくださいということもあるかもしれません。ですが結果的に孫子まで受け継がれていくものになるなら、その時間は有意義です。そうやって使う方に寄り添いつつ、常に材への尊敬を持ち続けたい。そういう姿勢で挑むことが、自然の材料を生かしきることであり、そういった仕事をしていくことが、先人である無名の名工たち、強いては僕の祖父への恩返しにつながるはずだと、僕は考えています。
自分にいい影響を与えられる
文化に密着した庭を──
ものづくりにおける僕のモットーは「無理がない」ことです。制作物が理に適っていることで依頼者の方の生活に寄り添い、ものも人も豊かに育つと考えています。
だから提案するのが庭であっても、硯を作るときと考え方はなんら変わりません。硯を例に挙げると、いい硯を買った、青栁に作ってもらった、でも勿体なくて使わなかったでは意味がないですよね。それと同じで、自分の思ういわゆる立派な庭を持った、でもちょっと手入れが大変で荒れてしまった、では寂しいでしょう。例えば僕が庭を造るならば、まず庭というものは人にとって一体何なのかを考えると思うんです。主な設置目的は実用なのか、鑑賞なのか。また、庭の機能に求めるものは人それぞれなので、その目的の要点が実生活で効果を発揮する着地点を模索します。そのためには庭文化の過去の実績を知ることは肝心です。